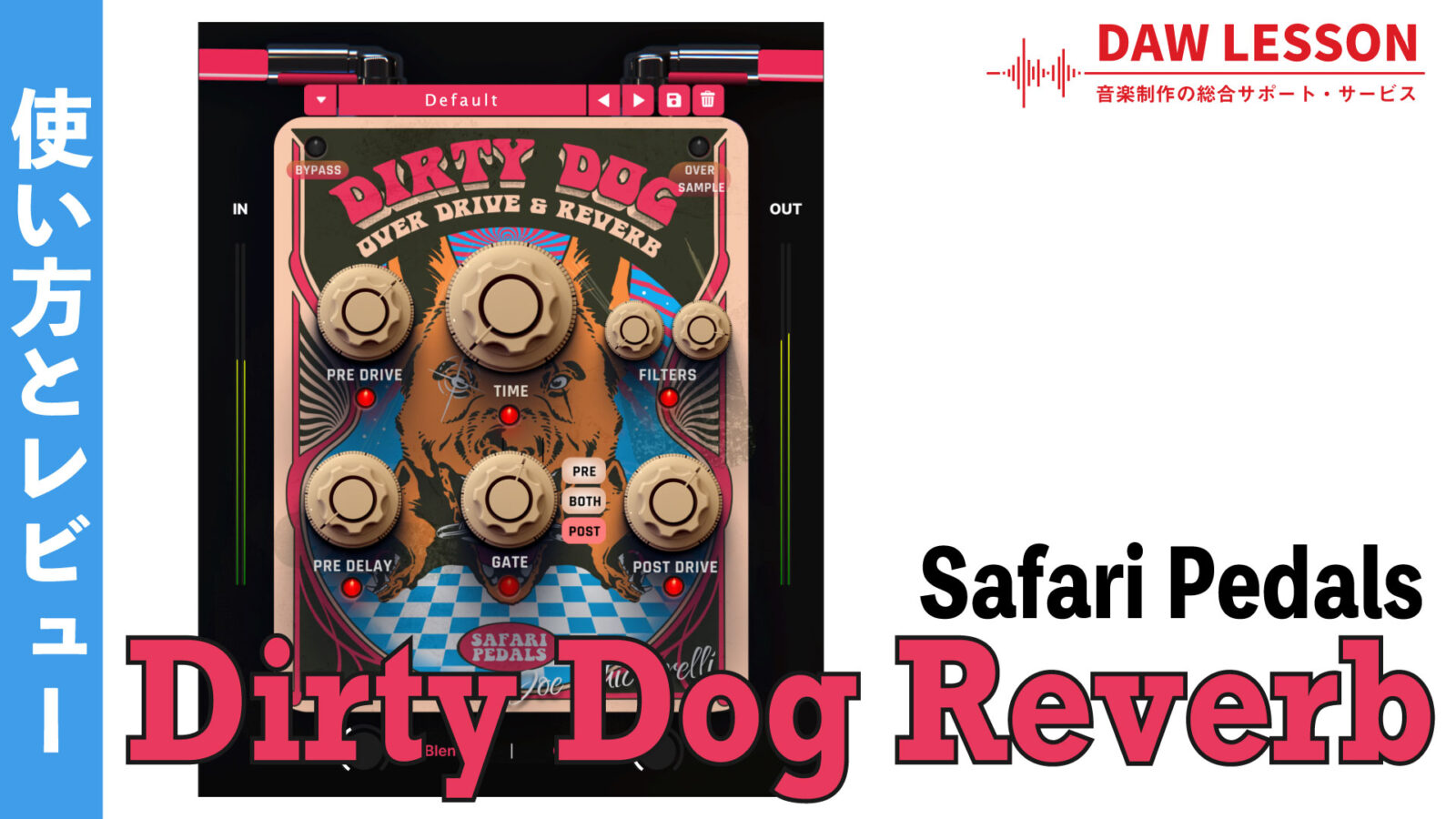TASCAM / DA-3000 レビュー
先日、デジタル一眼レフなるものを買ってしまいました。。思い返して見ると、自分でカメラを買ったのは始めてかもしれません。以前に使っていたコンデジも、最近使っていたデジイチも頂き物で…。業務上必要になることもあり、ようやく購入したところ、、
これがまた楽しい(笑)。正直、カメラに全然興味なかったんですが、ここ数日は意味もなくシャッターを切る生活だったりします。
前置きはこの位にして…。今回はTASCAMのリニアPCM/DSD対応のマスター・レコーダー「DA-3000」について書いてみようと思います。ここ最近、割と注目を集めているプロダクトではないでしょうか。先月末から使用しており、大分掴めてきたのでレビューにしてみたいと思います。
マスター・レコーダーとは
と、カッコ良いタイトルを付けてはみましたが… 要するにレコーダーです。なんでこんな機材が必要になるかというと、DAWソフト内でバウンスすると音が変わってしまうから。DAWソフトによっても変わってきますが、少なからず音質は変化してしまいます。
そこで “それなら、外部のレコーダーに録音すればいいんじゃね?” というシンプルかつ単純な(!?)製品が、このマスター・レコーダーなるアイテムです。自宅環境で完パケすることも少なくない昨今、何とかしたいな〜 と思っていたのですが、ようやくGET!
このカテゴリーでは、少し前にKORGのMR-2000が注目を集めていました。実際に触らせて頂いたこともあり、良いのは分かっていたのですが、レコーダーにいくら出すの? というコスト面の問題もあって先延ばしになっていたのですが…。先日、色々なタイミングが重ったこともあり、晴れて導入に至ったりします。
なお、DSDで録れる/聞けるというのも本モデルの特徴ですが、現状ではDSDは使っていません。
ハードウェア面
まず外観ですが、アルミ・フェイスに必要最低限のボタンのみという非常にシンプルかつ業務用機器を手がけるTASCAMらしい面構え。恐らく、メーカー写真で見るよりも実機の方が高級感を感じると思います。
ボタン類はクリック感がしっかりしているので、“押したつもりが押せてなかった”的なことも起こりにくいですし、LCDもコントラストがハッキリしているので、かなり見やすいです。そしてレベル・メーターもまったく問題なし。機敏に動いてくれます。
メニュー周りも非常にシンプルで、基本的にはJOGホイールだけで操作ができます。メニュー構造としては、すべてのメニューが一列に並んでいるのですが、「MENU」ボタンを押すごとにカテゴリごとにジャンプしていくというもので、迷わず使えます。未だ説明書は読んでません(苦笑)。
入出力
入出力関係も必要十分。まとめてみると、
・アナログ入出力:XLRバランス、RCAアンバランス
・デジタル入出力:S/PDIF(コアキシャル)、AES/EBU、SDIF-3
・ワード・クロック:1系統
と、必要十分。SDIF-3は、あまり録音機器で見かけることがない端子ですが、これはDSD伝送用のフォーマットですね。後発モデルということもあり、AES/EBUが追加されているのは嬉しいポイント。ワード・クロックはターミネートもできます。
メディア
最近だとSDカードの方が入手しやすいですが、どちらかと言えばCFカードがオススメでしょうか。サウンドも微妙に違いますし(意識しないと判別つかないレベルですが…)、本体のファーム・アップなどもCFカードが必要です。
また、電源ボタンの下にUSB B端子が2系統用意されていますが、ここにはファイル名を入力するためのキーボードと、USBメモリーを接続することができます。
USBメモリーは直接録音することはできず、SD/CFカードに録音したものをコピーするという形式。なお、USBメモリー内の音楽ファイルは直接再生することができます。
DAとして使ってみる
お使いのオーディオ・インターフェイスからどの程度のクオリティー・アップが望めるのか…というのが気になるポイントだと思います。個人的にも非常に気になっていた部分なのですが、想像以上に良かったです。
音を言葉で表現するのは難しいですが、全帯域できっちりと出しつつ、綺麗にまとまった音という印象です。バーブラウンのパーツ…とかマニアックなことよりも、主観ではありますが個人的な感想を書いてみたいと思います。
普段使っているApogeeのEnsembleはキラキラ系というか、ハデ目の音。曲作りやアレンジ段階では気持ち良いのですが、TDの段階だともう少し冷静に聞きたいな…と感じていたので、DA-3000のDAはかなりマッチ。本来あるべきところに収まってくれる感じです。なお、この傾向は、DA-3000をクロック・マスターにするとより顕著に表れてきます。
オーディオ・インターフェイスに限らず、音響製品を表すときに“原音に忠実な〜”なんて言葉を耳にするケースが多いと思いますが、誤解を恐れずに言うとどんな機器でも何かしらの色づけはあると感じています。メーカーによっても異なりますし、同じメーカーでもモデルや年代によってキャラは様々。
これがそのモデルの味で、魅力になるのだと思いますが、そういう意味でのDA-3000の印象は“原音のニュアンスをなるべく損なわないような、自然な色づけ”といった感じでしょうか。
唯一気になるとしたら、発熱でしょうか。ある程度は仕方ない部分はあると思いますし、パネルやボタンが熱くなるようなことはありませんが、結構熱を持ちます。特にラックマウントして使う場合、上部は1U開けておいた方が安心かもしれません。
音質云々については個人の好きこのみによる部分が多いと思いますので、参考程度に考えて頂きたいのですが、〜中級グレードのオーディオ・インターフェイスを使っている人は十分なクオリティー・アップが望めると思います。
ここ最近はDA-3000でDAしたソースをモニター・コントローラーに入れて作業していますが、まったく問題なく使えています。似た構成のUH-7000というオーディオ・インターフェイスもあるようなので、こちらをチョイスするというのもアリかもしれませんね。
バウンスと聞き比べてみる
ということで、実際にDAWソフトの内部バウンスで書き出したファイルと、DA-3000で録音したサウンドの比較サンプルを作ってみました。Logic Pro Xのバウンスとの比較で、どちらも24bit/48kHzのWAVファイルです。オーディオ・インターフェイスとDA-3000はデジタルで接続しています。
サンプル自体の作りが雑で申し訳ないのですが…(ミックス的なことも何もしていません)十分音の違いは分かって頂けるのではないかと。ちなみに、ドラムは発売されたばかりのAddictive Drums 2を使ってみました。こちらも近いうちにレビューしたいと思っています。
ストレージにもアップしましたので、興味のある方は聞き比べてみると面白いのではないでしょうか。。http://firestorage.jp/download/59d57e3b0feeb78b47b3fe67216aa437a6ef561d
ちょっとマニアックな機材ではありますが、バウンスしたときの音の変化が気になっている人、モニターのサウンドをグレード・アップしたい人にはかなりオススメの機器ではないでしょうか?
[amazonjs asin=”B00DY2C82E” locale=”JP” title=”TEAC マスターレコーダー/ADDAコンバーター 業務用 DA-3000″] [amazonjs asin=”B00I2E8TUO” locale=”JP” title=”TASCAM HDIAマイクプリアンプ搭載USBオーディオインターフェース UH-7000″]